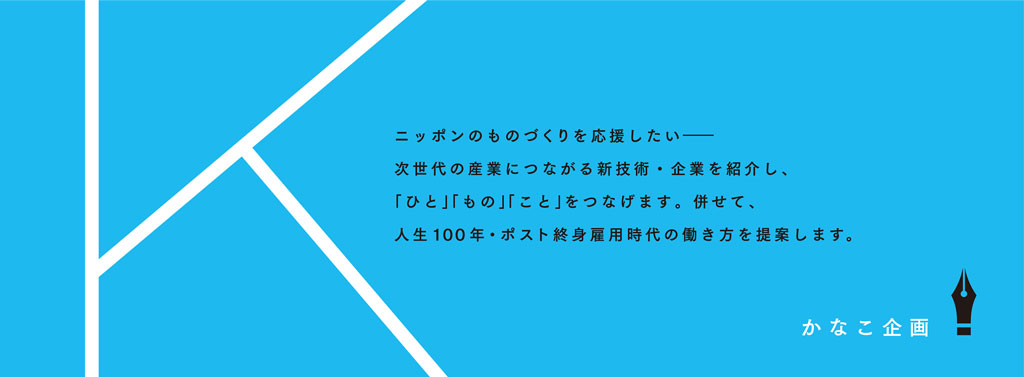NHK連続テレビ小説「ひよっこ」は多くの共感を呼んでいる
ちょうど50年前の昭和42年を描くNHK連続テレビ小説「ひよっこ」。現代日本を舞台にした日テレ系「過保護のカホコ」。働くことへの考え方が、この半世紀でどれだけ変化したかが両者で比較できる。貧しくとも「働く喜び」を謳歌できた昭和、豊かさゆえ「なぜ・何のために働くのか」と迷う平成。郷愁ではないが、現代人には、かつての純粋さがまぶしく感じられる。
「ひよっこ」の主人公みね子(有村架純)は、茨城県の農家の長女。出稼ぎ中に行方不明になった父の代わりに一家を支えるため、高校卒業後、集団就職で上京した。最初に働いた寮のある工場は倒産し、知己を頼って洋食店で店員として働く。1万円の月給の中から、半分を実家に仕送りし、アパート代を払い、つましく暮らしている。いま二十歳。
8月12日放送の第114回では、2年半ぶりに再会した記憶喪失の父と一緒に実家で田植えを終え、東京に帰って来る。田植えの翌朝、実家を去る時の独白が以下(みね子は独白で、いつも父に語り掛けている)だ。
「お父ちゃん。なんだか不思議な気持ちです。もちろん、うちは大好きで、ずーっとこのままいたいなあと思うけど、私の心の中に、早く東京に戻りたい、戻って、自分の場所で働きたい、という気持ちも強くあって」
「自分の場所」つまり居場所を東京に見つけたということだ。
店に戻ると、シェフ、女将さん、コックの4人が全員、「みね子」と呼びかけて歓待する。それぞれから、「ありがとな」「ありがと」と声を掛けられる。
自分の居場所があり、仲間がいて、感謝されて、働いている。贅沢はできないながらも、「普通に」生きることの喜び。だから、みね子はこう独白する。
「なんだか、忙しいのがうれしいんです。いろんなことが頭から抜けて(略)楽しいです。体が動きます」
お客が来る、席に案内する、注文を取る、料理を出す、片付ける、そうした一つひとつのことが、みね子は楽しくて仕方ない。余計なことを何も考える暇もなく、忙しく立ち働く時間がうれしい。結構な重労働である立ち仕事をリズミカルにこなす。シェフや女将らみんなも、笑って仕事をしている。忙しいけれど充実感はある。いいなあと思える光景だ。単純だが純粋な「労働の喜び」は、現代ではまぶしいくらいではないか。
働くことに意味などない。ただ「生計のために」、生きるためには働かざるを得ないから働いているだけだ。大きな目標に向かっている訳でもないし、大儲けすることもない。地味で地道ではあるが、こつこつ目の前のことをこなし、働いていけば、生きていける。明日は今日よりよくなると信じられたあの昭和の時代、日々を真面目に暮らすことは、明日への希望につながっていた。
翌日の店休日、みね子は同居している幼馴染に、もしかしたら、このまま実家から戻って来ないのじゃないかと、ちょっとだけ心配したと言われる。みね子は答える。
「なわけね。今は、この部屋が私のうちだもの」
改めて「おかえり」と親友に言われ、「ただいま」とみね子は返す。
みね子は、実家から離れて暮らす大都会・東京で、ついに自分の居場所を見つけたのだ。お店が働く場所。ここが私の家。だから楽しく誇らしいのだ。
(この項、「下」に続く)(2017・8・14、元沢賀南子執筆)