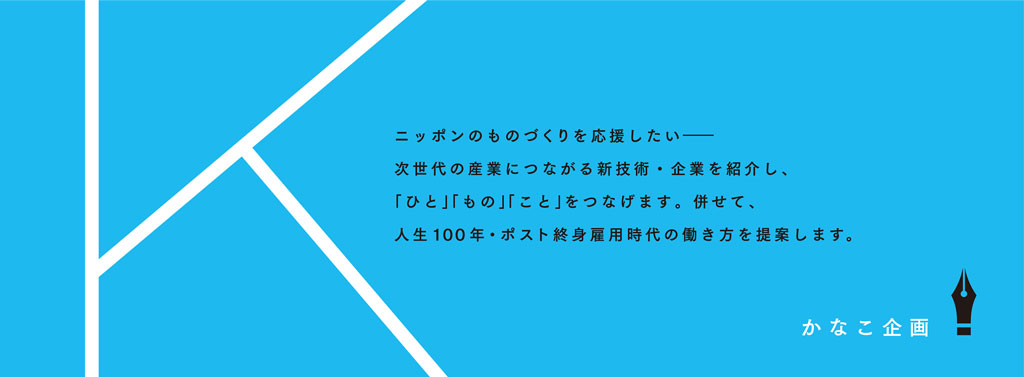NHK連続テレビ小説「ひよっこ」は多くの共感を呼んでいる
昭和42年の東京に自分の居場所を見つけ、仲間と働くことがうれしいと自覚する「ひよっこ」のみね子。50年前当時の、市井の人々の働き方を体現している。対照的に、「過保護のカホコ」は平成の現代に生きる大学4年生、21歳のカホコ(高畑充希)が主人公だ。
保険会社で働く父(時任三郎)、専業主婦の母(黒木瞳)は、ともにカホコに過干渉。朝夕、母に駅まで車で送迎してもらい、母の手作り弁当を食べる。自分で考えるより前に母から「こうしなさい」と提示されて育ってきた。就職活動は全滅し、母には花嫁修業を勧められる。
だが、それじゃ親から夫へと寄生先を変えるだけだと、同じ大学に通うハジメ(竹内涼真)に批判される。カホコは「人は何のために働くのか」と悩み、初めてのバイト体験で働いた後の食事のおいしさを知り、「人を幸せにする仕事がしたい」と気付く。
とはいえ、ここからが進まない。「人を幸せにする仕事」とは、カホコにとって何なのか。チェロリストを目指していた従妹は、ケガで夢を諦めざるを得なくなり、初恋の人ハジメは画家を目指している。「大事なことはネットには書いてない」と悟るが、では何をするか。
バイトやパートでも食べてはいける一方で、就職したところで明日会社がつぶれるかもしれない現代。今日より明日が幸せになると信じられず、会社や社会に希望が持てないからこそ、ならば「自分は」何をしたいのか、突き詰めて考えざるを得ない。
カホコには父母と暮らすマンションに自分の部屋もあり(みね子はアパート暮らしで初めて自分の部屋を持った)、貧しさとは無縁だ(みね子は実家に仕送りするため、月900円のお小遣いでやりくりしなくてはならない)。カホコは「生計のため」に働かざるを得ない訳ではないし、親にも「働く意義」のない労働は認めてもらえないだろう。その恵まれた環境は、もしかしたら逆に不幸なことかもしれない。
世間の波に揉まれまくるみね子に比べて、箱入り娘のカホコは世間知らずも甚だしい。20歳のみね子より21歳のカホコの方がずっと幼く見える。みね子は東京に戻る朝、不安そうな母親を励まし、「いやいや、私も大人になったもんだねえ」と茶化した。カホコはといえば、親離れするには、子離れできない母と闘わなくてはいけない。これが難敵だ。カホコの母自身も苦労知らずの世代だから仕方ないのかもしれないが。
ただ、周囲にも苦労人が多くいた昭和は、みね子も居場所を作りやすかった。仲間もできやすかった。苦労知らずで生きていける現代は逆に、仲間や居場所を、家族のほかに作ることは存外難しい。つながりたいと思って、つながる努力をしないとつながれない。家族だけで、家族という繭の中に閉じてしまうこともできる。
働くことに意味などなかった、生計のために働いた昭和と、働くことの意味や意義を考えざるを得ない平成。居場所や仲間が作りやすかった昭和と、居場所探しに皆が疲弊する平成。貧しかったけれど未来は明るいと信じられた昭和と、平均的に豊かではあるが未来に希望が持てない平成--こんなふうに見比べると、昭和がきらきらと輝いて見える。
でも、もしかしたら、すべては逆説的なパラドックスかもしれない。昭和の現実は貧しくて苦しくて我慢ばかりで、生きづらい部分もあっただろう。平成の方が生きやすい部分も大いにあるだろうから、そこに昭和的な発想法を取り入れることで、生き方や働き方を楽に変えられるかもしれない。
「働くことの意味や意義」はひとまず横に置き、単純に労働の喜びを体感できる仕事から始めてみたらどうだろう、とカホコに助言したくなる。
(この項終わり)(2017・8・14、元沢賀南子執筆)