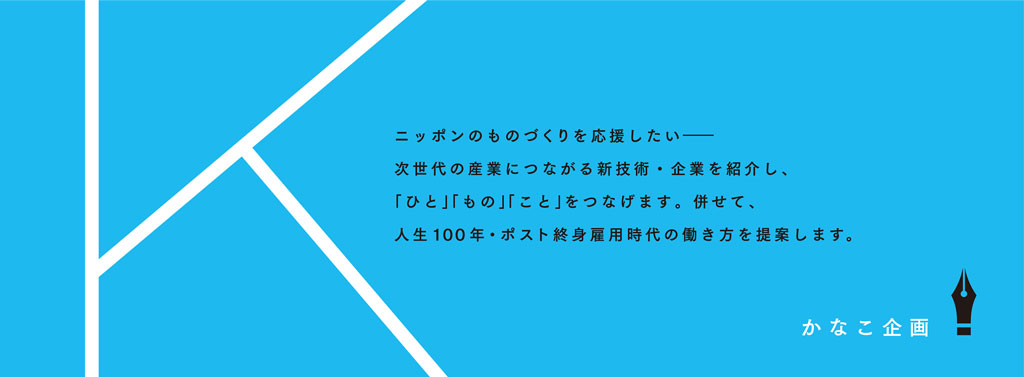「アザー・デザート・シティーズ」チラシ
より弱い家族を守るため、弱いからこそ権力を求めた――舞台「アザー・デザート・シティーズ」(ジョン・ロビン・ベイツ作、東京芸術劇場シアターウエスト)は、いさかいから真実の告白を経て相互理解に至る家族を描く。登場する家族は極めてアメリカ的な属性の人々だが、闘争は普遍的だ。弱い者を守ろうとして支配的になってしまう、家族という不毛な関係性について考えさせられた。
アメリカ西海岸に住む一家の居間が舞台だ。長女の作家ブルック(寺島しのぶ)が、クリスマス休暇でNYから里帰りして物語は始まる。
1幕の始め、共和党員の両親と政治的中立性を口にする長女との思想的な対立が描かれる(この辺り、翻訳・脚本の早船歌江子の仕事が出色だ)。俳優出身で元大使の父ライマン(斎藤歩)と、元脚本家の母ボリー(佐藤オリエ)は著名な共和党支持者。ボリーはかつて極右のティーパーティーにも関わっていた。ユダヤ人ながら、夫婦ともカソリックに改宗しているらしい。
同居している母の妹シルダ(麻実れい)とブルックはリベラルで、ロスのテレビ局でバラエティー番組を作る末息子トリップ(中村蒼)はノンポリ。政治的な立ち位置、宗教や思想信条の違い。そうした社会的で高度に知的な差異が、家族間の齟齬をもたらすのかと思われた。
だが舞台の進行につれて顕在化するのは、「庇護する者=母」「庇護される者=妹と長女」という支配・被支配の関係性だ。シルダはアル中だし、ブルックはかつて酷い鬱病で自殺願望があった。彼女たちを守り支え生かしたのはボリーだ。
ボリー曰く、「家族は一番弱い者に寄り掛かられる」。「家族だから、社会的道義的にそうしなきゃならない」。義務だから二人を守ったのだ、と。
家族とはいえ、一方は支配し、守り、立場が強く、他方は抑圧され、命じられ、立場が弱い。支配側からすれば正しく、当人のためを思っての言動も、被支配側からすれば、価値観の押しつけに過ぎない。だからシルダは「家族という奴隷制度に疲れた」と訴える。
庇護され支配されている側からの異議申し立ての象徴として登場するのが、長女が書き上げたばかりの2作目の作品だ。家族の負の歴史を暴く。
ずっと昔に亡くなった兄は、語られることも写真の一枚すらもない、家族間の禁忌だった。ベトナム戦争反対運動の末に爆破テロに関わり、守られるべき両親に見捨てられ拒否されたことで自殺した。その事実を世間に公表し、夫婦を断罪しよう。姉のプライドを砕きたいシルダも加担し、けしかける。美しく妖艶で危険な香りのする麻実が、「バラ色の人生(ラ・ヴィ・アン・ローズ)」を鼻歌で歌いながらはけて、1幕が下りる。

舞台「アザー・デザート・シティーズ」のチラシ裏面
第2幕に入り、長男という禁忌が触媒となり、家族の関係性は変化を始める。作品を発表すると譲らない長女と、「小説としては面白い」と話す母、茶化しながら間を取り持ち、いがみ合いを収めようとする次男。ここでの寺島と佐藤の闘いは見所の一つだ。
ボリーは、長女の書いた作品は出来事の全体像ではないと警告する。家族とはいえ、みなが家族のすべてを知っている訳ではない。それぞれ、自分が見ているものしか見えていない。「別々の真実の中で生きている」と。
そして、あと少し、せめて自分たちが他界するまで出版を待ってくれと頼む。だがブルックには、それは保身のためとしか思えない。母と姉の和解を諦めた次男が部屋を出て行った後、両親の「真実の告白」がなされる。
なぜ共和党だったのか。なぜ政治なのか。なぜ真実を子供たちには隠したのか。母は言う。「権力が必要だ。権力さえあれば隠し通せる」。弱くては家族は守れない。事実を隠すために、あえて権力に近づいたのだ。
強い母の涙ながらの告白で、ブルックとシルダは真実を知る。ブルックは作品が一面の真実でしかないことを悟り、自分を鬱に追い詰めていた原因――親友だと思っていた兄に見捨てられ、自分は価値のない人間だと思い込んでいたこと――が的外れだったことを知る。自己否定感から解放される。
真実によって、ようやく母娘は対等になれる。家族は理解し許しあう。
タイトルの「他の砂漠の町々」とは、舞台であるカリフォルニア州パームスプリングスと、家族の心象風景とを指しているのだろう。砂漠のように乾いた不毛の関係だった家族たちは、かろうじて父の死の前に融和を果たせた。真っ白で、ミニマリストの部屋のように最低限の装置しかない舞台(美術・島次郎)は、この家族の空疎さを視覚化して秀逸だ。
ブルックは結局、両親の死後ずっと経ってから作品を発表する。演出の熊林弘高は幕切れ、観客によもやの希望の光を見せる。そして、あれほどの砂嵐が吹き荒れた砂漠の町の物語は、何事もなかったかのように静かに終わる。(東京は7月26日まで。29日~31日、大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ)
(2017年7月19日観劇、元沢賀南子執筆)