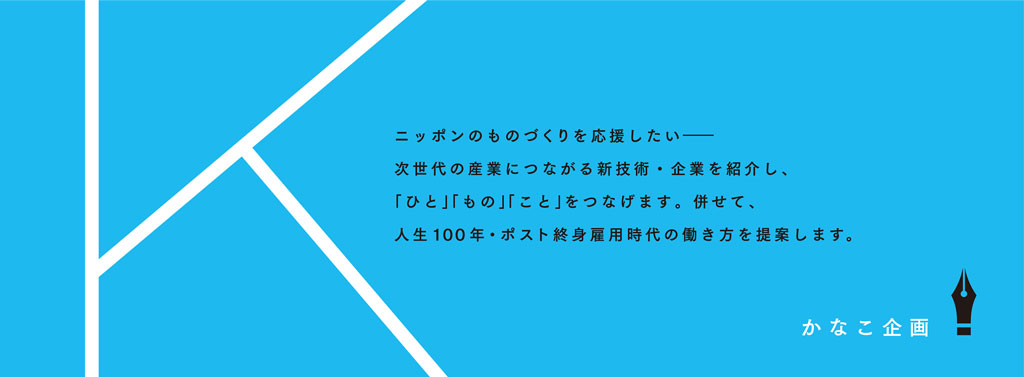ネット時代の新しい戦争「国vs個人」を描く
国家が監視する社会の恐怖
そして市民は負けた、のか
映画「スノーデン」評
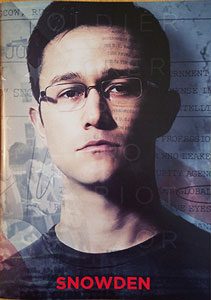
4年前に世界中を揺るがせたスノーデン事件。米政府が世界中の通話・通信データを傍受していたことを、元CIA職員が暴露したものだ。本作は、これをもとに、社会派オリバー・ストーン監督が製作した。「国家の戦争」を描いてきた監督ならでは、現代の「情報戦争」を舞台に国家と個人の対立を描き、監視社会の脅威を警告する。
主人公スノーデン(ジョセフ・ゴードンレビット)はコンピューターの天才だ。保守的な家庭に育ち、国に貢献したいと、情報技術の専門家としてCIAに入る。時は911後。政府は「戦争は中東ではなく、ウェブの中にある」と考えていた。秘密訓練を受けてスキルを磨き、実務へ。
そこで、米国が全世界の政治家ら要人だけでなく個人までも監視し、情報を収集している事実を知る。自分も監視されているのではないかという疑心暗鬼から、徐々に神経質になる主人公。しかも集めた情報を国家がどう悪用するかを知ってしまう。火のないところに煙を立てて火事場泥棒をはたらくようなやり口に、自ら任務でかかわったことがあった。
自らをなだめすかし、勤務地を変えて任務を続行。やがて、バックアップ用と指示されて、全世界の通信データを常時監視できるシステムを開発する。
そのプログラムを使った「誤爆」の瞬間の映像を見てしまう場面が、密かな山場だろう。アルカイダを捕捉し、無人機で空爆する。だが、対象の確認はおろそかで、民間人が多数犠牲になっていた。同僚たちが闘っている「作戦」は、遠く離れた安全な場所で家族と日常生活を送りながら、無線通信技術で、敵兵だけでなく民間人まで実弾で殺す手口だった。環境と行為の落差の異常さと違和感。
一方で、同盟国や敵対国ではなく、米国民の情報が最も収集されていた。かろうじて普通の人の感覚を忘れなかった彼の、組織への盲目的な忠誠心が揺らぎ始める。だがその直後、元教官であるCIA高官に脅され、恋人も監視されていることを知る。
味方をも監視し支配しようとする国。目を付けられた個人の、孤独で危険な国家との戦いが始まる。
それゆえのメディアへの密告だったと映画は動機づける。知らないうちに、許可もしていないのに監視する政府は正しいのか、国民に判断を託すためだと。
血も戦闘シーンもない「戦争映画」
ストーン監督の語り口はミステリーのように鮮やかだ。暴露を巡る主人公と記者とのじりじりするやりとりを現在進行形で見せつつ、主人公が組織を裏切るに至る経緯を過去に遡って時系列で追う。観客は、暴露の成功や、スノーデンと恋人のその後の無事を知っているにも関わらず、ハラハラする。彼も情報も「消されて」しまうのではないかと。
血も流れず戦闘シーンもないが、まぎれもない戦争映画である。誤爆への抗議が、ストーン監督を製作に向かわせた動機だったに違いない。「プラトーン」で監督は、ベトナム戦争の極限で心身を病む兵士を取り上げた。今作では、オフィスも海辺もホテルの部屋も、コンピューターのプログラミングと盗聴・遠隔操作のできるすべての場所が、情報戦の戦場になった。情報技術者はシステムだけ作ればいい、その活用法や戦略を考えるのは政権だ、とのCIA高官の警告は、情報技術者もまた戦場の兵士と同じ捨て駒に過ぎないことを示唆している。
だから、その「戦場」から生還した時、スノーデンは解放感にあふれた笑顔を見せる。自ら作ったシステムをコピーし、厳重な警備をかいくぐって、まんまと無事「外界」へ盗み出すことに成功した瞬間だ。記者たちに会うため香港に向かう。
ハッピーエンド!と思わせて、ストーン映画は辛口だ。我々への問いかけが残る。スノーデンが命がけで問うた命題は、その後どうなったのか。個人の自由やプライバシー保護を訴える世論は、報道後いったんは盛り上がり、オバマ政権は打撃を受け、情報監視の停止を命じた。だが現在は?
スノーデンはインタビューに答えて言う。人々はすぐに忘れる。慣れる。そして次に政権が交代したら、独裁者が誕生するだろう、と。
残念ながら、予言は的中してしまった。結局、スノーデンは賭けに負けたわけだ。彼を負けさせたのは、皮肉にも国家の剛腕ではない。当事者たる市民の、忘却と無関心と思考停止によって、だ。誰もがいつ、なぜかもわからず、無実の罪でも標的にされるかもしれない、にもかかわらず。そしてそれは米国だけではない。秘密保護法が通り、テロ対策の名の下に共謀罪が法制化されようとしている日本もまた同じ状況にある。
今作の完成はトランプ政権の誕生以前だ。ストーン監督の危機感と時代を読む感度に敬意を表する。そして、この映画を昨年、無事公開させた米国の映画人たちの心意気にも感服する。
願わくは、個人が自由でいられ、プライバシーが守られ、尊重される社会であり続けてほしい――その願いはすでに、子供っぽい情緒主義に過ぎるだろうか。(公開中)
(3月17日執筆)