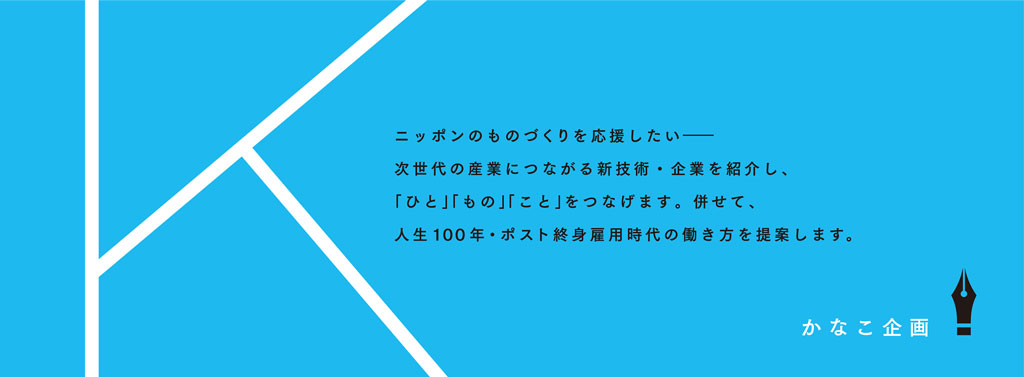春の甲子園が始まった。甲子園といえば、昨夏にスタンドで経験した異様な出来事を思い出す。
春の甲子園が始まった。甲子園といえば、昨夏にスタンドで経験した異様な出来事を思い出す。
選手権大会8日目の8月14日、八戸学院光星(青森)対東邦(愛知)の9回裏でのこと。5対9で負けていた東邦の攻撃は打順よく1番から。先頭打者が安打で出塁、球場全体が「何か」の予兆にざわめきだす。
1死2塁で3番打者が安打を放ち3点差に。続く飛球で2死1塁。これで終わりかもしれない、でも同点に追いつけるかもしれない。スタンド全体が東邦応援団と化していく。
もともと東邦側のアルプススタンドはブラスバンドの演奏がうまく、ノリノリの応援が続いていた。それが「野球は9回裏2死から」を地で行く展開で、「何かが起きること」への期待が一気に広まった。
筆者は銀傘下の特別自由席で見ていた。応援のうねりが球場全体を包んでいく。まるで夏の野外フェスのごとく、見渡すと、外野も内野も、ほぼすべての観客が東邦応援団のリズムに合わせてタオルを回していた。光星側アルプスのわずかな人々を除いて。
その時、隣に座っていた中年女性が、夫に言った。「こういう時は乗っとくもんよ」。そしてタオルをぶんぶんと振り回し始めた。
夫婦は地元大阪の高校野球ファンらしく、それまで特にどちらにも肩入れしていなかった。それが、タオル回しが伝わってくるや、「馬には乗ってみよ」とばかり、飛びついたのだ。
その女性の感覚は、ごく普通なのだろう。波が来たら乗る。流行には食らいつく。みんながしているから、自分も一緒に参加する。その方がきっと楽しいから。
だが私は気持ちが悪かった。異常だと思った。同調圧力がかかっているわけでもない環境で、なぜみな、自ら、波にのみ込まれに行くのか。なぜ周囲に流されるのか。熱に浮かされ、同じことをするのか。これがいわゆる共同幻想か。
試合後に光星の投手は言っていた。「球場全体が敵だった」と。事実、あの場の異様な応援の渦は、マウンド上の桜井投手をひどく孤独にしたことだろう。
判官びいきが弱い者いじめに
観客たちは最初は単純に、負けているチームを応援する「判官びいき」だったに違いない。最後の最後まで諦めないプレーに、高校野球のすがすがしさを感じたかっただけかもしれない。
ところが意に反して、「期待した通り」に、「奇跡」が起きてしまう。観覧席に戸惑いが漂い始めるのは、東邦が同点に追いついた頃からだ。ふと気付けば、いつしか、みんなでよってたかって弱い者いじめをしていた構図になっていた。連続安打で東邦は同点となり、逆転の5点目を入れ、あれよあれよという間に、光星はサヨナラ負けを喫してしまった。
光星ナインと桜井投手を孤独にさせ、追い詰め、委縮させ、打ち負かしたのは、東邦の果敢な攻めではない。観客席の異様なほど圧倒的な声援だったろう。
その場にいた私は、ただ怖かった。多数派や時代の気分はこうして形成されるのだ。タオル回しの熱狂は、リアル世界での「炎上」だ。熱が熱を呼び、どんどん暴力的にヒートアップしていく。人々は、かくも簡単に、長いものに巻かれるのだ、と思い知った。
それはつまり、「寄らば大樹の陰」「付和雷同」という群衆心理を利用すれば、人々を一方向へ操作することはさほど難しくはない、ということでもある。人々に、自らの意志で進んで参加させることができる。ひとたび流れが決まれば、途中で止められない。
しかも、大衆という、無名で無責任な傍観者たちの、その後の変わり身の早さと冷たさも、見てしまった。
試合が終わると、熱は急速に去った。スタンドに残ったのは、ばつの悪そうな空気だけだ。一種の罪悪感のような後味の悪さ、しらけたような、他人事のような冷めた雰囲気。「波に乗っかっていた」だけの人々が、ふと我に返って青ざめたのだ。
光星を負かしてしまったその責任の一端が、もしかして自分にもあるかもしれない。意図しなかったが、相手をいじめ、傷つけ、陥れ、打ち負かすことに加担していたのかもしれない。加害者になっていたことに思い至った瞬間、人々は目が覚める。さっと身をかわし、過去から距離を取る。自分には責任はないと、何事もなかったかのように振る舞い、忘れたがる。
事実、そういうふうにして戦後、人々はさまざまなことを忘れてきた。
「右へ倣え」「長いものに巻かれよ」の国民性は、そうそう簡単に変わるものではないだろう。「のど元過ぎれば熱さ忘れる」の性質も。70年以上昔も今も、きっと。
それが怖い。
(2017年3月22日、元沢賀南子執筆)