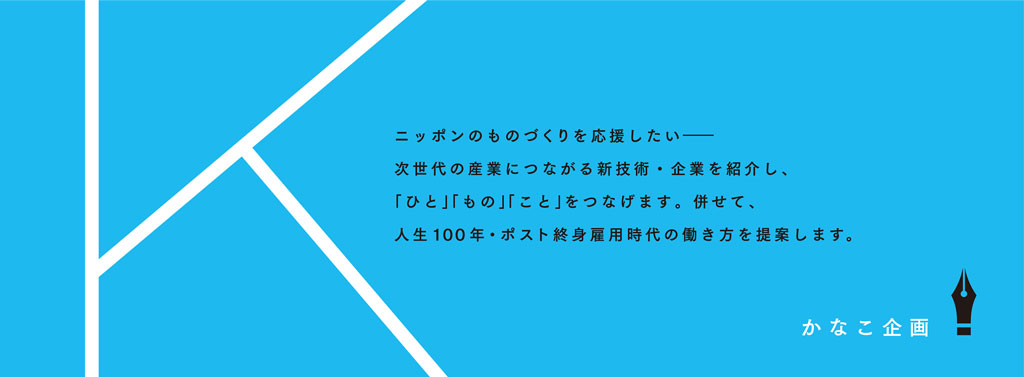母と子の物語
「父親不在・アンチ家父長制」のファンタジー世界で描かれるLGBT
映画「彼らが本気で編むときは、」評
 映画「彼らが本気で編むときは、」は、「かもめ食堂」「めがね」等で癒し系と称された荻上直子監督の最新作。やはり癒し系になった。「父親」不在の世界での、母子の愛を描く。子を思う母という主題は、脚本も書いた荻上監督の、出産後の初作品であることが大きく影響したに違いない。
映画「彼らが本気で編むときは、」は、「かもめ食堂」「めがね」等で癒し系と称された荻上直子監督の最新作。やはり癒し系になった。「父親」不在の世界での、母子の愛を描く。子を思う母という主題は、脚本も書いた荻上監督の、出産後の初作品であることが大きく影響したに違いない。
4組の母子関係が描かれる。小学5年生のトモ(柿原りんか)とシングルマザーの母ヒロミ(ミムラ)。ヒロミと弟マキオ(桐谷健太)と、その母(りりィ)。マキオの恋人リンコ(生田斗真)とその母(田中美佐子)。トモの同級生の男児カイとその母(小池栄子)。
ネグレクト気味の母に失踪され、叔父マキオを訪ねたトモは、リンコに出会う。手つきや所作は女性っぽく美しいものの、トランスジェンダーであるリンコに、トモは興味深々だ。そんなトモにリンコの母は、最愛の娘を傷つけるなとすごむ。
リンコが働く老人施設には、マキオとヒロミの母が認知症で入っている。トモの同級生カイは男の子が好きなのだが、その母はリンコの存在を否定し、近づくなといさめる。
どの母も子を愛してはいる。だがヒロミは食事もろくに作らず男と出奔してしまうし、ヒロミの母は昔から娘に厳しかった。カイの母はカイに良かれと思うあまり、価値観を押し付け、わが子の気持ちを踏みにじってしまう。
すべてを受容するのは、リンコの母とリンコ、つまりは荻上監督のやさしさだ。
母の愛を感じられずにいたトモは妙に大人びた子供だった。最初は斜に構えるが、リンコに食事や弁当を作ってもらい、髪をとかしてもらい、一緒の布団で抱きしめられて眠るうち、打ちとけていく。
トモがリンコの胸を触らせてもらって「赤ちゃん返り」する場面がいい。「愛され直す」ことで、やがて素直さを取り戻す。子育てのこのディテールはさすが荻上監督だ。虐待を受けた子を養子に受け入れた家庭でよく聞く逸話だ。親代わりの大人にちゃんと大事にされることで、子どもは安心して自分自身を認められるようになる。
 子供だけの閉じた世界の幸福
子供だけの閉じた世界の幸福
一方で、作品の世界観を形作る最大の特色でもあり、同時に欠点にもなっているのが、父親の不在という点だ。リンコの父もマキオたちの父も早くに亡くなり、トモは父を知らない。カイの家庭にはおそらくいるはずだが、画面には現れない。リンコの母の再婚相手はあくまで母の夫であり、リンコの父ではない。
父親は、物語にしばしば世間の常識や社会的な壁の暗喩として登場する。強権を発動する暴力的な家父長的存在に怯えることなく、今作では安心して荻上監督の世界観に浸ることができる。だがその心地よさと引き換えに、現実味が薄れファンタジーになってしまった。
荻上監督は「癒してなるものか」と社会派を宣言して、LGBTという日本では取り上げられにくい題材を選んだ。多様な人々の存在が無視されている現代日本への違和感が動機だったと語る。だが女性たちの多様性が描かれるほど、古い考えを振りかざす典型的な旧世代の男性の不存在は、逆に目立つ。残念ながら「現代のおとぎ話」になってしまった。もちろん、リアリズムの追及だけが正しい作劇術ではないが。
トモだけでなくリンコもマキオも実は、親ではないという意味で子供の立場のままだ。経済的には自立しているものの、子供3人の暮らしは閉じた世界だ。おままごとのように、誰にも干渉されず傷つけられもしない。やさしく穏やか、かつ平和で幸福な場所。
おとぎ話には必ず終わりがある。子供たちの閉じた理想郷は、親の登場で終止符を打たれる。ここでも親は父ではなく、母ヒロミなのだが。ヒロミはリンコを、暴力ではなく言葉で、面と向かって「母ではない」「女でもない」と、否定する。対してリンコは「人として」反論する。
これは監督のメッセージだろう。母として子供を守るための「世間」との闘い。子供たちが将来どんな人生を選んだとしても生きやすい社会であってほしいという純粋な願いが透けて見える。
最後、トモは少しだけ大人になる。願わくは、子供たち3人が、子供でいられた空間での満ち足りた感覚をいつまでも忘れずに生きていけますように。そう観客に思わせて、静かに物語は終わる。現実にはない安心感に抱かれて。
(2017年3月25日執筆)
(写真はいずれも映画パンフレットから)