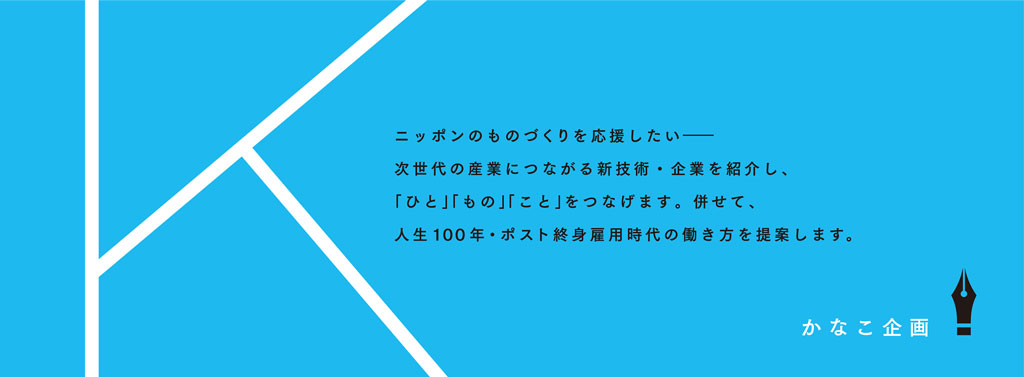騒がれ荒らされ「そして誰もいなくなった」
イルカ漁の町と捕鯨問題を描く

「おクジラさま」は9月9日から東京・渋谷ユーロスペースなど、全国で順次公開予定
なるべく全体像を見せたいという佐々木芽生(めぐみ)監督のジャーナリスティックな視点で製作された映画「おクジラさま」は、周囲に翻弄される「和歌山県太地町(たいじちょう)」が主人公である。伝統的なイルカ漁が、反捕鯨映画「ザ・コーヴ」で動物虐待だと非難され、世界中の注目を集めたのが2009年。以来、様々な人や団体が次々と勝手に押し寄せては、意見を言い、行動し、やがて去った。突然の大嵐が過ぎて後に残ったのは、荒らされ傷ついた小さな地方都市だ。
佐々木監督は淡々と、起きている事象を映し出す。
海外の環境保護団体の反捕鯨運動家は、SNSなど最新メディアで、感情に訴えるライブ動画や英文記事を世界中に配信する。右翼風の日本人は漁師の立場を支持する。捕鯨の歴史、食用鯨肉の含有水銀問題、需要減で価格が下がり成り立たなくなってきた食用鯨肉産業。鯨肉は食べないのに日本人の7割が捕鯨に賛成なのは、伝統や文化に対して欧米の価値観が押し付けられることへの反発からだとの分析。
食用より高額な水族館向けの生体捕獲が、実は太地町の捕鯨産業の柱になっている。反捕鯨派は生体を買う側に圧力をかける戦略へと転換、主張が「殺すな、食べるな」から「捕獲した生体を買うな、動物の権利に反するイルカショーなどの生体展示はやめろ」へ移った。世界中の世論を味方につけた動物愛護運動は、捕鯨産業を細らせ、水族館の在り方までも変えさせる――クジラ・イルカを巡る論点は多岐にわたり、町民も含めて人々の意見はそれぞれだ。発信力のある側に取材源を依存するが故の、マスメディアの視点の偏りも指摘される。
映画は、米国人ジャーナリストの視点と思考を案内役に据える。彼は長く日本に住んでいたが太地町に移住、時間をかけて町に溶け込んだ。町民に、ほとんど更新しない日本語のウエブページでは、英語で日に何度も配信する反捕鯨派の世論形成に勝てないと伝え、情報発信を助言する。差を埋めるべく、町の言い分も入れた記事を英字誌で書く。

映画「おクジラさま」のチラシ(表・裏)と、クジラ模様がかわいいパンフレット(左下)
暮らすうちに彼は、捕鯨問題とは無関係の争点に気づく。飲み仲間や挨拶する小学生ができ、人々の温かさに触れた。祭りや濃密な人間関係があるコミュニティー、地域共同体の一員になったのだ。
それが残る地方はローカルルール(自国第一主義)を求め、失ってしまった都市はグローバリゼーションに恩恵を感じる。両者の経済的な対立、心情的な分断は世界各国で起きており、欧米では政治すら動かしている。太地町はある意味、ローカルとグローバルという文明の衝突の現場ともいえる。
印象的なのはエンドロールだ。取材(2010年4月~16年7月)の後の、登場人物の顛末を短く伝える。反捕鯨運動家だった外国人夫婦も、右翼的な日本人支援家も、活動を「足抜け」。海外の環境運動家らは主戦場を別の土地に移し、ジャーナリストの彼すら米国で暮らす。ほとんどの人々が、町にはもう来ない。

「おクジラさま」は編集に約1年かかったという。監督・プロデュースの佐々木芽生氏=日本記者クラブで、8月4日
英題は「A WHALE OF A TALE」。直訳すると「お話のクジラ」だが、英語で「a whale of~」は「とんでもなく大きな~」という意の慣用句。監督はそれをもじって「とんでもないおハナシ」としたそうだ。嵐に巻き込まれた太地町にとって、それこそ、とんでもない話だった。
(9月9日から東京・渋谷ユーロスペースほか、順次全国で公開予定)
(2017・8・31、元沢賀南子執筆)