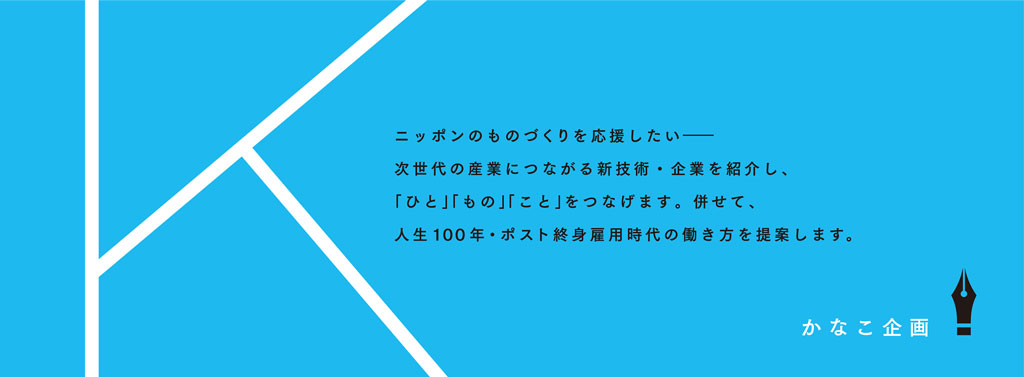段田安則のコメディアンぶりが楽しい、チェーホフ作「ワーニャ叔父さん」のパンフレット。新国立劇場で9月26日まで
チェーホフの描く19世紀末ロシアの閉塞感は、現代日本に通じる。中高年の勤め人ならきっと共感するのが、ケラリーノ・サンドロヴィッチ演出・上演台本「ワーニャ叔父さん」(東京・新国立劇場で上演中)だ。自分を認めて欲しいとジタバタしたり、退職後のアイデンティティー・クライシスに苦しんだり、財産を巡って親族が争ったり。滑稽なまでの姿は1世紀を経て国境を越えても変わらない。
47歳のワーニャ(段田安則)は、亡き妹の娘ソーニャ(黒木華)と農園を管理している。食費すら削って、ソーニャの父の大学教授に送ってきた。退官した彼が、27歳の美しい後妻エレーナ(宮沢りえ)と訪れ、物語は始まる。教授とワーニャは、連日真夜中まで飲み、昼過ぎまで寝てはまた飲む。尊大で病気持ちの教授は医師の診察を避け続け、医師とワーニャはエレーナに夢中。医師にはソーニャが6年間も片思いだ。
1幕は舞台が半透明のカーテンで覆われている(美術・伊藤雅子)。登場人物のもやもやした心理状態の暗喩でもあり、ロシアの農村に立ち込める朝霧のようでもある。
その靄の中で、男たちは不満をつぶやく。ワーニャは、教授に自分の働きを認めて欲しい。教授はもっと有名になりたい、成功したい。医師は、目先の利益に捕らわれて森林環境破壊を続ける農民や社会を批判する。みなが誰かに認めて欲しい。
2幕ではカーテンが取り払われ、恥ずかしいほどに明るい中、本音が顕わになる。ワーニャも医師も、エレーナを堂々と口説き、エレーナと医師の濡れ場をワーニャは見てしまう。教授は皆に、老後資金のために農園を売って投資すると宣言し、ワーニャの怒りが爆発。農園の所有者はソーニャだし、25年間も全財産と人生を捧げてきたのに、と教授を責め、銃で襲う。教授は売却話を撤回。夫妻も医師も去る。農村には再び、静寂と地味な日常が戻る。

ケラ演出、上演台本による「ワーニャ叔父さん」のポスター。黒木華の恥じらいがかわいく、宮沢りえはファムファタルぶりを発揮する。9月26日まで新国立劇場で
「仕事」がキーワードだ。教授が他人事みたいに「諸君、仕事を」とたきつけて消えた後、ワーニャは「さ、仕事だ仕事」と自らを鼓舞して仕事を再開。年ごろのソーニャは「仕方がない」と、死ぬまで人のために働く人生を受け入れ、諦めている。歯車のまま、収奪される日々。
単調になりがちな物語を、ケラの演出は適度な笑いで救う。段田の明るいキャラとも相まって、劇に色彩を与える。だが、教授一行=非日常が去った後は、滑稽味と彩りが抜け、ずしりと重いモノクロの日常だけが残る。「さあ、働かなければ」という感覚がひしひしと胸に迫る。
教授は、現代の労働者にとっては会社に当たるだろう。過去半世紀、私生活もなく不満を押し殺して働き、今後もそう続けるしかないワーニャの絶望は、1世紀後の勤め人にもしみじみと伝わる。(9月26日まで)
(2017・8・28観劇、元沢賀南子)